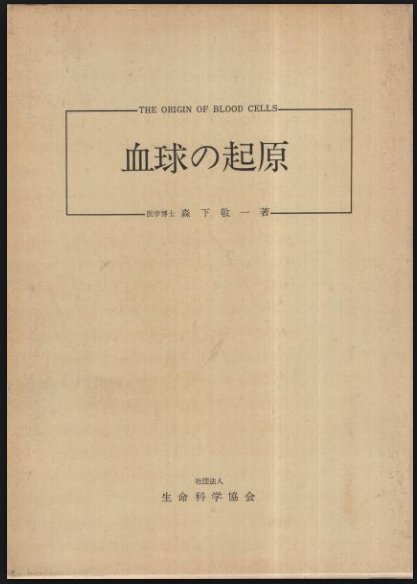造血について
血液はどこで造られているのか?
骨髄が腸か?
(天動説と地々地動説)
ガン治療は、このままで良いのか?
その昔、国会にて、こんなことがあったんです。
それぞれに感じ取ってください。
そのときの議事録です。そのままどうぞ。
第058回国会 科学技術振興対策特別委員会 第6号
昭和四十三年三月二十一日(木曜日)
午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 沖本 泰幸君
理事 小宮山重四郎君 理事 齋藤 憲三君
理事 始関 伊平君 理事 石川 次夫君
理事 三宅 正一君 理事 内海 清君
大石 八治君 岡本 茂君
桂木 鉄夫君 角屋堅次郎君
三木 喜夫君 近江巳記夫君
出席政府委員
科学技術政務次官 天野 光晴君
科学技術庁長官官房長 馬場 一也君
科学技術庁研究調整局長 梅澤 邦臣君
科学技術庁振興局長 谷敷 寛君
科学技術庁資源局長 鈴木 春夫君
厚生省環境衛生局長 松尾 正雄君
委員外の出席者
厚生省医務局総務課長 上村 一君
厚生省国立がんセンター病院長 塚本 憲甫君
農林省農政局参事官 田所 萠君
農林省農政局植物防疫課長 安尾 俊君
農林省農業技術研究所病理昆虫部長 岩田 吉人君
工業技術院総務部総務課長 片山 石郎君
工業技術院発酵研究所長 七字 三郎君
参 考 人
(東京都葛飾赤十字血液センター所長) 森下 敬一君
(佐久総合病院健康管理部長) 松島 松翠君
(理化学研究所副理事長) 住木 諭介君
(理化学研究所主任研究員) 見里 朝正君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
科学技術振興対策に関する件(対ガン科学、農薬の残留毒性の科学的究明及び低温流通機構等に関する問題)
――――◇―――――
○沖本委員長 これより会議を開きます。
科学技術振興対策に関する件について調査を進めます。
対ガン科学に関する問題調査のため、本日、参考人として東京都葛飾赤十字血液センター所長森下敬一君に御出席を願っております。
この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、御多用のところ、本委員会に御出席くださいまして、まことにありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べくださるようお願い申し上げます。
なお、御意見の聴取は、質疑応答の形でお述べいただきたいと存じますので、さよう御了承願います。
質疑の申し出がありますので、これを許します。斎藤憲三君。
○齋藤(憲)委員
厚生省その他から係官御出席と思いますが、いまわが国のガンに対する関係機関及びその予算をひとつ概略お知らせを願いたい。
○上村説明員
厚生省の行なっておりますガン対策でございますが、特にガン対策として取り上げましたのは昭和四十一年度ごろからでございます。そのころからガンの専門医療施設の整備でありますとか、あるいは研究の助成でありますとか、あるいは医師等専門職員の技術向上のための研修、そういう
ものをやってまいりまして、四十三年度の予算案では、厚生省関係の経費といたしまして二十六億七千万円計上いたしております。
やっております施策の第一点は、ガン診療施設の整備でございます。これは国立がんセンターを中心にいたしまして、全国のブロックに地方ガンセンターを設け、各都道府県にガン診療施設というものを整備してガン診療施設を組織的に体系化をはかりたいというのがねらいでございます。先ほど申し上げました二十七億円の予算の中でこのために充てておりますのが二十一億七千万円でございます。これが第一点。
それから第二点は医師等の専門技術者の養成でございますが、いま申し上げましたガン診療施設の整備に合わせまして、ガン診療に従事する医師でありますとか、あるいは診療X線技師その他の技能を向上させるために、当初は国立がんセンターをはじめとする三つの施設で、四十二年度からは四つの施設で、毎年研修を実施いたしております。
それからガン対策の第三点としましては、ガン研究の推進でございます。厚生省では臨床部門における研究を、文部省では学術研究をというふうに、役割りを分けていたしておりますが、四十三年度予算は、厚生省で行ないます臨床部門における研究につきましては二億五千七百万円、このために計上いたしておりま
す。
それから最後が集団検診でございます。ガンの早期発見のために集団検診を実施しておりますが、四十三年度予算案ではこのために二億三千万円計上いたしまして、胃ガンなり子宮ガンの集団検診車の整備でありますとか運営の補助、それから、こういった集団検診に従事する技術職員の研修を行なっておるわけでございます。
以上が、厚生省が中心になって行なっておりますガン対策の概要なり、その予算額でございます。
お話しになりましたガンの関係機関というものはどういうものがあるかというふうなお話でございますが、診療施設、研究施設、それから研修施設を兼ねましたものとして国立がんセンターがございます。それからいま八つのブロックに国立なりあるいは公立の地方ガンセンターというのがございますが、ここでは診療と、それから研修、場合によれば研究も行なうようにいたしております。その他、先ほど申し上げましたように、都道府県単位でガン診療施設というものを国立病院あるいは公立病院に整備いたすことにいたしております。
これが厚生省の関係でございますが、その他、科学技術庁なり文部省の関係がございます。民間のものとしては、御案内の癌研究会が持っております研究所なり病院があるわけでございます。
○齋藤(憲)委員
文部省来ていますか。――文部省の研究体制を係官が見えたら伺いますが、ただいまのガンに対する厚生省の施策というものは、ようやく本格的になったという感じをいたすのでございますが、このガンに対する研究体制、民間との接触というものは一体どういうところで行なっているのですか。民間の研究体制、それから厚生省の研究体制、そういう、何らか連携を保って広くガン問題に取り組んでいるというような体制はあるのですか。
○上村説明員
先ほど申し上げました、厚生省で計上しておりますガンの研究費につきましては、国立がんセンターの中にガン研究の助成金の運営打ち合せ会というのを持ちまして、そこでガン研究の助成金の交付対象となるような研究課題の選考なり、それからそういった課題に対しまして交付しようとする研究費の予定額の作成、こういつた仕事をしておるわけでございます。そして、この打ち合せ会は、がんセンターの総長を会長にいたしまして、関係行政機関なり国立がんセンターの職員、それから学識経験のある方々にお願い申し上げまして、そうして、いま申し上げましたような仕事をしておるわけでございます。研究課題につきましてこの打ち合せ会できめましたものを公募いたしまして、公募されたものに対しまして、いま申し上げました打ち合せ会で検討して、必要な研究費を交付するというような扱いをしております。したがいまして、いま御設問のようなところは、厚生省が持っておりますガン研究費を配分する過程の中で行なわれるということになるわけでございます。
○齋藤(憲)委員
現在のガンにおかされておるいわゆる罹病者の数ですね、大体でけっこうですが。それから年々どのくらい死亡しているか、それからこれは一体ふえているのか減っているのか、これを簡単に、もしわかったらお知らせを願いたいのです。
○上村説明員
ただいま、ガンにおかされておる患者の数というのは、手元に正確な数字の持ち合わせがございませんが、ガンによって死亡した者の数でございますが、御案内のように、ここ十年以上もわが国の死亡率の中で一番上位を占めておりますのが脳卒中でございますが、悪性新生物による死亡というのは昭和二十八年以来その二位になっております。それで人口十万対比で見てまいりますと、昭和二十八年に悪性新生物による死亡が二位になったわけでございますが、人口十万対比で八二、それが毎年伸びてまいっております。そういたしまして四十一年では、二十八年に八二であったものが人口十万対比で一一
〇・八になっております。この間の十数年間というのは、毎年人口十万当たりの死亡率というのは高くなってきております。
○齋藤(憲)委員
そうしますと、毎年ガンの研究に多額の研究費をつぎ込み、そうして、ガンに対する設備を拡充し、そして、ガンの死亡率がふえているということになりますと、結局いまやっていることはガンの実体を把握しないということですね。どう考えますか。その点もし研究が効率をあげて、そして、ガンの実体を把握して、それに対する対症療法というものが着々功を奏すれば、ガンの死亡率というものは減っていかなければならないわけです。 それがだんだんガンの死亡率が高まっていくということは、ガンに対する今日の知識では押さえ切れないというのか、それともまた、ほかの現象で、早期発見によってガンというものが多くなっておるのか、そういう点についてひとつ……。
○上村説明員
いまお話しのように、年々ガン死亡率というのは高くなっておりますが、それはその研究が実態に合わないからといいますよりも、むしろ先ほどお話しになりましたように、早期診断によってガンとして診断されることが確実になってまいったということが考えられますというのが一つと、もう一つは、寿命が延びてまいりまして、ガンにかかる年齢の階層というものがふえてまいったことも一つの原因じゃなかろうかというふうに考えます。
○齋藤(憲)委員
実は、私、きょう対ガン問題に関してここで質問をしたい、こういう考え方を持ちましたのは、この間新聞に、富国生命が小児ガンに対して毎年一億円ずつ十年間寄付をするという記事が出たのです。これを読みますと、ガンによって小さな子供が毎年生命を奪われる数というものは千五百人にのぼっておるという。これが小さな子供としての生命を奪われる病気においては最高の率を示しておるのだという記事であります。それを読みますと、ただいま御説明がありましたように、寿命が延びたからガンの率が高くなったということには、これは当てはまらぬ。小児ガンなんだ。小児ガンがだんだん年々死亡率が高くなって、ついに子供の死亡率の最高を示す病気だということなんです。いまのお話とはこれは合わないのですね。ですから、私はもちろんそういう 生命が延長されて、そこにガン患者もたくさん出るかもしれないし、あるいは早期発見によってガンの確率が高まるということもあるかもしらぬけれども、小さな子供の死亡率がガンによって年々高められておるということからいうと、結局、ガンというものは、幾ら金をつぎ込んで研究をやってみても、はっきりしたガ ンに対する根本的な病理学的な結論というものは見出し得ないのだというふうに考えるのですが、どうですか。がんセンターの塚本病院長、そういう点どういう ふうにお考えになりますか。
○塚本説明員
私がこれから申し述べることが斎藤先生の御期待に沿うかどうか別問題でございますが、ただいまの、小児のガンがふえているというので、寿命が延長したということと話が別じゃないかというお考え、一応ごもっとものように思えるのでございますが、ガンの占める中では、先ほど申し上
げましたように十四歳くらいまでを含めましても千四百とか千五百とかいう実数が出ております。したがいまして、全体からいうと、そのふえ方のプロポーションというものはそう大きくはないと思います。ただ、小児のガンがなぜふえてきているかという問題になりますと、非常にむずかしいいろいろな問題もございますし、この小児のガンと称するものの大部分が白血病であるということ、それからまた、そのほかには、先天的なかなりの異常によって生後にガン化したものがかなり含まれている。そういう二つのことを考えますと、ほかのガンでも近来非常にふえているものがあったり、この説明はまちまちでありますし、非常にむずかしい問題で、なかなか軽率に予断は許されませんけれども、ある学者は、小児のガンがふえてきているのは、かなり妊娠中に放射線を使うというような問題もふえてきておるであろうし、放射線との関係を否定することはできないという考えの人もありますが、実際の研究に基づいてそういうはっきりした数字がまだ出ておりません。
それからもう一つは、白血病の発生というものは食物、ことに栄養価の高い食べものと関係があるということを言う学者もございます。そういうことを見ますと、われわれが子供のときに食べていたものから見ますと、いまの子供ははるかにいい栄養をとっておりますし、たん白質もふえております。ネズミの実験で恐縮ですが、同じネズミに白血病をつくります実験で、いい食餌をとらせるとパーセンテージがふえてくるなどということから、そういうことを言っておる学者もありますが、これも私はその真偽のほどはよくわかりません。
大体そういうことが、小児のガンがふえているということに関して私の知っておることであります。
○齋藤(憲)委員
まあ世間では、ガンはタブーだ、あまりガンということを口にすると、それは人格を疑われるぞというまでガンというものは 非常にむずかしい問題だと私は思います。ああすればガンがなおるとか、これがガンの原因だとかということは、今日の医学の進歩においても、その原因を追求してもなかなか追求し切れない大きなむずかしい問題だと思うのです。
〔委員長退席、内海(清)委員長代理着席〕
私、きょう特にこの委員会で、本来ならば関係各大臣御出席のもとにこの問題をひとつ考えていただきたいと思ったのでありますが、そういうふうにもまいりませんでしたが、出席の厚生省及び科学技術庁に一つ問題を提起して御回答を得たいと思いますことは、昭和三十七年の四月二十五日に科学技術振興対策特別委員会で、ガンの問題に対するディスカッションをやったわけであります。それに出席をせられましたのは、なくなられました田崎勇三博士、それから東京医科歯科大学の太田邦夫博士、それからSICの牛山医学博士、東京慈恵会医科大学付属東京病院の荻原医学博士、こういう方が参考人になって、そしてここで終日ガンのディスカッションをやったわけであります。それは牛山博士のSICというものは鼻くそだ、こう田崎勇三博士が言ったということが週刊雑誌に出たわけです。それをこの委員会で取り上げまして、いろいろ論議を重ねたのでありますが、そのときに私は、これを読みますと、もう六、七年前のこの記事でございますが、こういうことを言っている。自分はこの委員会において、牛山博士のつくられたSICという注射薬がガンに効果があるとかないとかということを取り上げて問題にするのではない。牛山博士と田崎勇三博士のSICに対する考え方の食い違いをただすのだ。というのは、この牛山博士がSICの製造方法に対しまして、ガン患者の静脈血を無菌的に取って、その血漿を分離してこれを無菌五プロのポリタミンの中に培養していくんだ。そうすると、そこに点の細菌があらわれる。それが十日ほどたつと球菌に成長していく。さらに温度を適正にし、数日これを培養していくと桿菌になる。その桿菌をタンク培養して、その代謝産物を精製して、そうしてこれを注射薬にする。SICというものはこういうものなんです。ところが田崎博士は、そんなばかなことはない。カエルの子はカエルで、ヘビの子はヘビだ。点菌が球菌になって、球菌が桿菌になって、そうして、代謝産物を注射薬にするというとガンにきくなんということはもってもないことであるということなんですね。私がこの委員会のときに執拗に当局に要求をいたしましたのは、どっちが正しいか実験をするということが必要じゃないか。田崎博士は、ガンの大家として、オーソドックスな最高の地位にある。その田崎博士が、牛山博士のSICをつくる過程における点菌、球菌、桿菌という過程というものは、そんなことはあり得ないのだ。一方、牛山博士は、田崎博士は勉強していないのだ、あなたはちっとも実験していないからそういうことを言うのだ、あなたは時代おくれの勉強なんだという論争だったのです。だから、これを厚生省は実験しろ、しかもガラス張りの中で実験しろ、立ち会い実験をやれ、これは何でも
ないことだということで、そのときの尾崎医務局長に言うたのですけれども、とうとうやれないのです。金は科学技術庁の調整費を出すというところまでいったのです。ところが実験をやれないのです。どういうわけか、どうしても実験をやれない。それに対してたびたび要望書というものが出てきたのです。ここへきょう参考人としておいでになっております森下博士も名を連ねておりますが、岐阜大学教授の千島博士、東京新宿日赤病院長の鈴木博士、東京竹内病院の長嶋博士、それから化成協会物性研究所の高橋医学博士が名前を連ねて、私あてに、ガン研究推進のためSICを含む諸問題の客観的な検討を政府に要望いたします
と、要望書が来たのです。それでまたやったのです。これでもってSICに対して三回やっているのです。どうして実験をしないのか、どうしても厚生省はこの
実験をやらないのです。予算がないというから、それじゃ科学技術庁の調整費を出して、じゃ実験をやってくれ、それでもやらない。いまだにやらないのです。
そうして、牛山博士はこの間の、昭和四十一年四月七日、ぼくは落選して、おらなかったときです。その速記録を見ると、牛山博士はここへ来ているのだ。そうして、やはり同じことを言っている。一体そういうことがあっていいものかどうかということなんですね。それは七、八年も、しかも国会でもって四回も同じ問題を追及して、そうして、科学技術的に検討を加えるべき重大な問題に対して、科学技術庁は調整費を出しましょう、こう言っているのに、厚生省はその実験を拒否してやらない。そういうことがあっていいものかどうかということを私は非常に疑問に思っているのですが、これは大臣に聞くのがほんとうなんだけれど も、大臣代理と思ってひとつ答弁してください。――それじゃそれをひとつあとで検討しておいてください。これは重大な問題だと思うのです。だから私はさっきも申し上げたとおりに、SICがガンというものに対して効果があるとかないとかということを取り上げているのじゃないのですよ。こういうことは国会において取り上ぐべきものじゃないと私は思う。SICというものはガンにきいてもきかなくても私には関係ないんだ。ただ問題になったのは、SICを製造する過程における、ガン患者から無菌的に血液をとって、それをセントリーフユガールにかけて、血球と血漿を分離して、その血漿を五プロのポリタミンに培養する。そうすると微生物が発生してくる。それをさらに培養していくと、今度はそれが大きくなって球菌になっていく。それをさらに培養していくと桿菌になっていく
という。それが鼻くそだと田崎博士は言う。これは冥途に行かれたから、ガンで倒れられたからあれだけれども、速記録を見るとよくわかる。それが正しいか正しくないか、どっちが一体正しいんだということの追求を科学技術庁の調整費でもって厚生省にやってくださいといっても、とうとういまだにやらない。それ
じゃ二十七億円ガン対策のために金をかけているといったって、そういう肝心のところはやらないんだ。一体どういう研究をやっているのか。これは非常に広範にわたるでしょうから、ここでどうのこうのというわけじゃありませんが、それはひとつあなたのほうでもよく考えていただきたい。だから、いまから問題にすれば、SICというものを実験の対象として取り上げてくれるかどうか。ここに科学技術庁の政務次官がおられますから、科学技術庁に頼んで、調整費から実験費を出してもらう。こんなものは幾らも要りはしない。そういうところをガンの研究において長らくの間論議されたのですから、これはひとつ取り上げてもらいたいと思いますが、一体そういう研究をやってないのですか、そういう実験をやってないんですか。どなたでもいいんですが。
○内海(清)委員長代理
ちょっと齋藤委員に申し上げますが、さっきの御質問のは、いま厚生省のほうに当たっております。それで大臣と局長は、参議院の予算委員会で来れないそうですから、政務次官にでも来てもらおうかということで、いま当たっております。お含み願います。
○塚本説明員
私はそのころにまだがんセンターにおりませんでしたのでよく存じませんが、第五十一回の科学技術振興対策特別委員会の議事録がここにございます。これを見ますと、がんセンターにおいても久留博士のところでSICに対する実験をやっておられます。それはおそらく科学技術のほうの予算ですか、厚生省の予算でしょうかわかりませんけれども、がんセンターでやっておって、その結果がマイナスに出ているということが書いてあります。あまり詳しい御説明は避けますが、これを読んでいただければわかるのではないかと思います。ですから、先ほど齋藤委員がおっしゃったように、全然手をつけずに
拒否しているというわけではないと私は了解しております。
○齋藤(憲)委員
それは、SICをいじった人はたくさんあるんですよ。SICの否定論というものは、私はやってみた、私はやってみたなんだ。そうじゃないんです。私の要求しているのは、なぜ牛山博士にやらせぬかということです。ガラス張りの中で。
一体あらゆる生産事業というものは、特許権よりはノーハウが大切なんです。それを、SICを取り扱ったこともない者が、どういう観点でもってSICの実験をやるのかわからぬ。それでマイナスだという。それは発明者を冒讀するものです。なぜ一体発明者にやらせないんだ。だから私が要求しておるのは、ガラス張りの中でSICの発明者である牛山博士にやらせなさい。そうして、顕微鏡はみんなでのぞけばいいじゃないか。ところが、私やりました、私やりましたというが、一体だれが証人としてそれを見ておったのです。そういうことは発明者を冒讀する実験というものです。なぜ一体ガラス張りの中ではっきりした体制で
もってやれぬのか。どうなんです。
○塚本説明員
私がいま申し上げましたのは、牛山さんがおつくりになったSICを使って、確かなガン患者に用いて、その効果を見たという意味で、これは別に牛山氏のそのつくる過程についていろいろ議論したわけではございませんけれども、その結果がネガチブだったということを申し上げたのであります。
○齋藤(憲)委員
私が言っておるのは、SICが病人にきいたとかきかないということを問題にしておるんじゃないということを言っておるのでありまして、SICをつくる過程において、点菌が球菌になり、球菌が桿菌になって、そうして、その代謝産物の精製物がSICになっておるんだという牛山博士の主張に対し、田崎博士は、そんなばかなことはない、点菌が球菌になり、球菌が桿菌になるなんていうことは、カエルがヘビになったのと同じことだから、それは鼻くそだと言った。その実験をやりなさいと言っておる。それをやらないのです。だから、それだけ学問上において大きな差異を来たしておるところのものに対して調整費を出すから実験をやってくれ、しかもガラス張りでやってくれ、その発明者がみずから立って実験をやるやつを、周囲から正当な実験であるか実験でないかということをはっきり監視しながら立ち合い実験をやってくれというのに、厚生省はやれない。そういうことがあったんでは私は研究費というものははっきりした体制において使われていないのじゃないかと思うのです。それはセンターの病院長としてどうお考えになりますか。
○塚本説明員
どうもSICに関してしろうとだものですからお答えがあまりうまくできないかもしれませんが、いまのように球菌が桿菌になったり、また、それがどうなるとかいうようなことが、そういう実験の間に行なわれ、それがガンにきくというような、そういうことまでわれわれの常識は進んでおりませんので、それは、つまりできたもの自身が効果があるないでこの段階では判定するよりしようがないじゃないかと思います。ただ、細菌学的には非常にそういうことは奇妙なことで、おそらくそういう意味で故田崎博士がそういう極言を使ったという形であらわしたのではないかと想像いたします。
○齋藤(憲)委員
これは水かけ論になりますからやめますが、点菌が球菌に成長し、球菌が桿菌に成長するということがないと言うなら、それは、ダーウィンの進化論というものはのっけから否定してかからなければならぬ。そうでしょう。そういうことがあり得るかあり得ないかということを確かめるのが実験なのですから、SICがガンにきくとかきかないとか、そんなものはわれわれ問題にしていません。そういうことでこの論争を科学技術振興対策特別委員会で取り上げたんじゃないのです。はたしてそういう現象というものが微生物の世界にあるのかないのかということを追求しようということが論争の焦点であった。それを厚生省がやれないというなら、微生物というものの進化というものに対して厚生省は何らの責任も興味も持っていないということだな、逆から言うと、やらないんだから。尾崎医務局長に対してこれは執拗に迫っておるが、どうしてもやると言わない。そうして最後に尾崎医務局長が私に言ってきたのは、
何とかプライベートにやらしてくれ。私は、プライベートに実験なんかやってもらう必要はない、やはり公式の実験をやってもらうということを要求したが、とうとうやれなかった。だから、これは今後もひとつ問題として残しておきたいと思います。
〔内海委員長代理退席、委員長着席〕
いずれ文書なり何なりで大臣あてに要望しておこうと思っておりますから、あまりこういう問題で時間をとるというと本論に入らないことになりますからやめます。
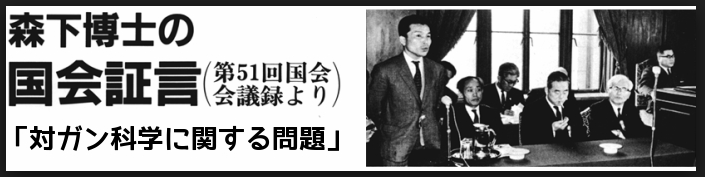
ところが、この第五十一回国会科学技術振興対策特別委員会の議事録第十四号というのを読みますと、きょう参考人としておいでを願いました森下敬一博士の 参考人としての陳述がここへ出ておるのでありますが、これを読みまして、一体こういう陳述がこの委員会で行なわれたのに対し、どうして問題にならないでこれがほっておかれるかということです。というのは、当時の文部事務官の渡辺大学学術局情報図書館課長も来ておられます。これはどういう関係で来られたか。
厚生事務官の公衆衛生局企画課長の宮田千秋さん、厚生事務官、医務局総務課長の中村一成さん、厚生技官の国立がんセンター病院長、それから牛山さんと、いろいろな人が出ておられますが、ここで森下博士が陳述をしておられるのです。これは私落選しておるときですから、知らなかったのです。そうしたところが、
こういう本を私は手に入れたのです。こういう「血液とガン」という本があるから手にとってみたところが、社会党の原代議士が委員長の席についておる。これ はまさしく部屋も国会の委員会ですね。ところが、うしろをひっくり返してみたところが、第五十一回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録と書いてある。それで非常に興味を持って私は読みました。ところが、これはたいへんなことが書いてある。一体なぜこれが物議の種をかもさないで平穏に過ごされておるのかということであります。それでお忙しい中を御本人の森下博士においでを願って、きょうはわずかな時間でありますけれども、ここでひとつ論争の種を植えておきたい。きょう一回で終わらないですよ、大問題ですから。
第一に、森下博士の国会における陳述というのは、「このガン問題というのは、私たちが十年ほど前から提唱しております新しい血液理論というものを土台にしなければ、ほんとうの対策というものは立てられないのではないかというような考え方を持っております。」こう述べておられるですね。そうして、血は骨髄でできるものではない。骨髄で血ができると考えておるのがいまの医学のガンだ、
血は腸でつくられるのだ、
こういうことが一つですね。
それから、ガン細胞は 分裂増殖しない。
それから、赤血球は可逆的な作用を持っておる。まだほかにも書いてございますが、時間もございませんから私なるべく簡潔にきょうの焦点をしぼりたいと思うのでありますけれども、森下博士に伺いたいのですが、一体われわれしろうとは、食ったものが血になるのだと、こう考えておる。それは食ったものが血になるのでしょう。その食ったものが血になるということは、胃と腸とでもって血をつくるのだと、こう考えておる。なぜ一体事新しくここへ血は腸でできるのだということ、いわゆる腸の血造説を持ち出しておられるのか。ほんとうに現在の医学では、血は骨髄でできると考えておるのですか、それをひとつ
伺いたいのです。
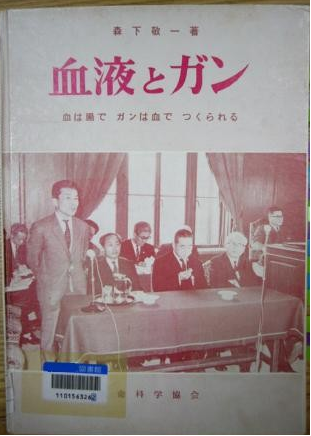
○森下参考人
現在の定説では、赤血球、それから白血球の一部は、いわゆる骨髄組織の中で生産されているというのが世界の定説であります。 しかし、この考え方にはたいへんいろいろ矛盾あるいは不合理な点がございまして、私、かれこれ約二十年ばかり血液の生理学をずっと、現在でも学んでおるものでありますが、そういう立場から考えてみますと、非常に大きな問題をはらんでいる定説であるというふうに考えておりまして、実際にいろいろと実験を行なってみますと、現在信じられている定説であるこの骨髄造血説は明かに間違いである。実際に、私たちのからだの中を流れている血球細胞というものは腸でつくられているということを確証いたしました。これを提唱したのは十年ほど前であります。以来これは正式に、もちろん生理学会をはじめとしていろいろな学会で提唱いたしておりますが、ほとんど顧みられている学説ではございませんで、極端に申し上げれば、黙殺されているという状態であります。しかし、いま斎藤委員がおっしゃいましたように、これは、常識的に考えてもわかることでありますが、われわれ日常の食物が実際に消化液の作用を受けて、そうして、これが腸の粘膜の中に取り込まれて、赤血球という細胞につくりかえられておるというふうに理解すべき問題である。そういうことを、私たちは科学的な立場で、科学的に実証したということであります。
○齋藤(憲)委員
そうすると、骨髄は血をつくるのだ、従来はこの学説によって医学の根本的な考え方がきまっておる、こういうことですか。 ――そうすると、生物が生命を保持していく上において、特に動物世界において、血液によって細胞が全部培養されていく、その血液が腸でできるのだという説と、骨髄でできるのだという説とが分離しておっては、そこから一切の医学的な考え方というものは違っていくんじゃないかと思うのですが、それはどうですか。それじゃ、そこからいろいろな医学的な考え方というものは違っていくのですか。
○森下参考人
私たちの新しい血液理論によりますと、食べ物が腸の粘膜で赤血球という細胞に変わりまして、この赤血球がからだの中を循環いたしまして、すべての体細胞に変わっていっております。肝臓の細胞も、ひ臓の細胞も、あるいは皮下脂肪であるとか、骨髄脂肪であるとか、あるいは筋肉の組織もまた赤血球からつくられているのでありまして、言いかえますならば、食べ物は血になり、そして血は肉になるという東洋古来の考え方に逢着するわけであります。こういう理念というものが現代医学あるいは生命科学の中に存在しておらないということが、数々の問題を引き起こしている根本的な原因である。現在
ガンをはじめとして文明病というものが盛んに広がりつつありますけれども、こういう病気がなぜ起こるのか、あるいは、それに対する対策というものがなぜできないのかということをいろいろ突き詰めてまいりますと、食べものが血になり、血が肉に変わっていっている。そして、この血液と体細胞との間に可逆的な関係がある。血が肉になったり肉が血になったりというような、そういうダイナミックなものの考え方が存在しておらないというところにほんとうの原因があるというふうに私は考えております。
であるがゆえに、われわれの血液理論というものが、文明病対策の根本理念として取り上げられなければならないであろうし、あるいはわれわれが建康長寿を保つというような意味でも、こういう考え方をぜひとも理解する必要があるということを約十年来私たち提唱してまいったわけであります。
○齋藤(憲)委員
そうすると、いまのお話によりますれば、食べた食物は腸の粘膜を通して赤血球になる、そして、あらゆる組織をつくっていく。が、しかし、場合によっては、その赤血球によってつくられたあらゆる体内の組織というものは、可逆作用によってまた血に戻り得る、その血に戻り得るときに骨髄の作用を必要とするんだということですね、ここに書いてあることは。まあそれに対してはさらに、現代の医学からいきますと大いに反論があると思います。これは根本的な問題でありますから。その反論を承っておりますと時間がありませんから、いずれこの次にその反論を承りたいと思います。これは重大問題です。
それからもう一つ。ここに、ガン細胞は分裂増殖しない、これは赤血球がガン細胞に変わるんだ、赤血球が常に何らかの作用によってガン細胞に変わっていくんだから、それは分裂しないし、増殖しない。これはたいへんなんです。私がいままで読んだ――私のところにも、興味を持って何十冊というガンの本がある。 が、しかし、その中の大半は、ガン細胞の分裂増殖、きわめて急速なガン細胞の分裂増殖と書いてあるんですがね。ここなんです。それを、どうしてこういう大きな新しい――正しい説であるかどうかはわからぬとしても、いやしくも医学博士の学位を持ち、そうして、赤十字の血液センターの所長をしておる地位にあって、どういうことで参考人としてこの委員会に呼ばれたのか、その当時のことはよくわかりませんけれども、とにかく、その当時の委員及び委最長のいろいろな相談の結果、適当であるとして呼ばれたんだろうと思うのです。ここでこういう陳述をしておるのです。ガン細胞は分裂増殖しない。これはたいへんなことですよ。もしガン細胞が分裂増殖しないということが正しいとしたら、いままでのガンに対するいろいろな説というものは全部間違いだということなんです。私の知っている限りでは全部間違いだということになる。どうですか、これは、病院長。
○塚本説明員
私は血液生理の専門家でありませんが、先ほどの血液のことも含めてお答え申し上げますと、われわれは、体細胞が異常な増殖をし、どんどん分裂してできた腫物をガンと言っているのでありますが、ガン細胞が分裂しないということは、根本から反対になっているわけです。
○齋藤(憲)委員
ここで、きょう委員会を開いていただいて、参考人に来ていただいて貴重な時間をいただいた価値が出てきたわけです。一方は、ガン細胞というものは、赤血球が血液の状態によって異種細胞に変化していくのだ。だから、赤血球が異種細胞に変化していくのだから、次から次にガン細胞ができていって、そのガン細胞というものは何も分裂繁殖しないのだ。どんどんふえていくんだ、めちゃくちゃにふえていくことはふえていくんだけれども、そのふえ方というものは、決して細胞の分裂増殖によらないのだ、赤血球がガン細胞に変わっていくのだという、これは森下博士の説ですね。ところが塚本国立がんセンター病院長は、単細胞が分裂繁殖していくのだから、そういう説に対してはまっこうから反対だ。さあこの実験をひとつやってもらいたい。これだけ
はっきりした対立というものが浮かび上がった以上は、これはどうしても科学技術振興のたてまえから解決していかなければならぬわけです。これは政務次官どうですか。こういう問題を解決していくのに調整費というものがあるので、いままで科学技術庁ではガンに対して三回調整費を出しておる。その金額は大体一億円に近い。何の目標に向かって調整費を出したか、調整費を出した目標と結論というものを私は聞いておりませんけれども、進歩に対する効果というものは全然なかったように私は思う。ですから、こういうように、
一方は、血液が変形をしてガン細胞をつくっていくのだ、
一方では単細胞が、いわゆるガン細胞が一つできると、いまの病院長のお話だと血液の中にガン細胞が一つできると、これがどんどん分裂繁殖していってたくさんになってくる。
全然根本的に違うんですね。
こういうところを詰めていかないと、私はやはりガン問題というものは解決しないと思う。科学技術庁はガンに対しても大いに取り組んでおられるのですからこ
ういう問題を取り上げて、お金がなかったら調整費から出してやる、それでどっちが正しいかという実験をやるということを私はお願いしたいのですが、どうですか。
○梅澤政府委員
ガンの問題につきましては、先生先ほどおっしゃいましたように、第四十国会のときにこの委員会で取り上げられました。それが三十七年でございます。それから三十八、九年まで私のほうの特調費で、できるだけガンの厚生省の研究に補強の金を出しまして、四十年ごろから厚生省のほうでガンを重要対策に取り上げましてガンの研究費はそこから相当ふえてまいりました。そして現在までまいりましたので、私たちのほうは特調費でガンのほうの補助をしておったということであります。その間に確かに問題はSIC等にて起こりました。この件につきまして、厚生省とわれわれのほうと御連絡をとりましたが、いわばこの研究を事実上――ちょっと私も昔のことで忘れておりますが、引き受けてやってくださる研究者を見つけるところに非常な苦労があったのが厚生省だと思います。したがいまして、私どもは、調整費がございますから、これからも厚生省のほうと十分に御連絡してやらせていただきたいと思います。
○三宅委員
関連して。ただいまの斎藤委員の御報告、私、実に重大だと思うのです。私自体、ガンに対して学会から治療界から非常な努力をしておられることは承知しておりますが、実にガンの診断についても治療についてもこれからだと思うのです。現に私の非常に印象に残っておりますことは、私の知人が背中が痛くて痛くてどうしようもないというので、方々の医者に見てもらったがどうしてもわからない。癌研で田崎先生にお願いをいたしまして、レントゲンをうんととってもらった。そうしたところが、田崎先生が私にレントゲンを見せられまして、ガンのけは全然ないと言っておられましたけれども、痛みは去らない。その後、結局背骨のりしろのところにガンがありまして、順天堂病院でその人は死んだのであります。そして、御本人の田崎先生自体もガンでなくなられたのであります。私は、そういう意味におきまして、ほんとうにどうにもならぬことをガンというのですから、ガンというだけあって、いかにガンというものが業病であるかということを痛感いたします。そういう意味におきまして、世界的に現代の医学が追求いたしまして、ガンに対しましては、その原因がわかって
おるかどうか知りませんが、原因についても、いま申されましたとおり、森下さんといろいろ意見が違ったりいたします。ほんとうにまだ模索の状態ではないかと思うのであります。したがいまして、そういう意味においても、行政府なんというものが、こういう学術的なことについて、内容に干渉すべきではないけれども、学界における偏見であるとか、派閥であるとか、そういうものに左右されて、民間の医者の中で、とんちんかんな議論が出ることもあるでしょう。あるけれども、ほんとうにわかっていないし、日本の最高の権威である癌研においても、たった一週間か二週間前の、背骨のうしろにガンがあるのがいまのレントゲンではわからぬで、最後にわかって、順天堂で死んだというような事態を見ても、その意味において行政府は、学界におけるそういう論争などに対して金を出したり、いろいろいたしまして、それぞれ全体として発展させるということが、私は、その任務じゃないか、研究調整費の任務じゃないかと思う。斎藤君が、さっきの問題についてあとにするなんと言っておられますけれども、こういう問題については、ほんとうに幅広く論争させたり、それに便宜を与えたりする。先入観を
持たない。厚生省の医務局長が、オーソドックスの医学者として、学界における定説を支持される、それはよろしい。けれども、こういうわかっておらない問題については、
異説に対してだって相当に金をかけるべきだと思うのであります。
時間がいただければ、私はついでに質問いたしますけれども、たとえば、小児ガンなんというものは、実は私はこの間までほとんど知らなかったのであります。そして、いまも承りますと、白血病が原因だというか、白血病のことを言っておられますけれども、私は、小児ガンの増加などについては、最近の科学技術の発展による公害関係の影響があるのではないかということを、私ども医学に全くしろうとの直観で感ずるのであります。特に、きょうこれからやります農薬の問題などについて、ともかく、われわれの子供のときには、チョウチョウは飛んでおる、バッタは飛んでおる、ドジョウはおる、タニシはおるということで、田
園というものが実に楽しかったのでありますけれども、これがおらなくなってしまった。それによっていもち病がなくなったということはけっこうだけれども、
同時に米の中に農薬の悪い、ほかの動物を殺しましたものが入っておりまして、それをたくさん食っておりまする間に人間の生命に大きな影響を及ぼすということは、しろうとの感覚のほうが正しいと私は思うのであります。そういう意味におきましても、あとからもう一ぺん時間をいただいて、小児ガンのことについて は聞きまするけれども、ただいまの斎藤君の議論は、ひとつ委員長が扱われまして、委員会全体の意見として、ひとつそれをやらしたらいいと思うのであります。やってもらわなければならない。ともかく、研究をして、一つの意見を出して、それが学界の定説と違ったからといって、ただ排撃するのではなしに、公平な立場で試験する。それ自体にはたいした権威がなかったけれども、その付属物で何か大きな発見があったりすることがままあるのですからして、私は、そういう点は、斎藤君の意見を委員会としてもほんとうに支持してやらなければならないと思いますから、ちょっと関連発言を求めた次第であります。田崎さんの話も出ましたので、ひとつ病院長から、私の発言に対して御答弁がありましたら答弁なり、教えていただくことがありましたら教えていただきたいと思います。
○塚本説明員
いまの小児ガンの問題、そういうことがどういうことからふえてきたかというようなことですが、いろいろ――御説のとおりであります。
ただ、誤解がございましたようですから、もう一ぺん私から斎藤議員に対してもお答えさせていただきますと、単細胞からガンができるのではなくて、からだのどこかの細胞、体細胞、それが、何の原因かわかりませんけれども、あるときにそういう変な細胞に変わって、どんどん分裂して増殖していくのがガンだということを私はいま申し上げた。これが一つであります。
それから血液とガンの関係、これは、私は血液の生理学者でございませんから詳しいことは存じませんけれども、放射線でガンをなおすという立場から私たちが従来やってきましたことから申し上げますと、先ほど申し上げましたように、体細胞からできますから、胃からできたガンは、胃の粘膜の構造がどこかに残っ
ているような意味のガンになります。これをわれわれは腺ガンと申しております。皮膚からできたものは、皮膚の構造を残しながら、非常に鬼っ子になって、こういうところにかいようができたりしてまいります。一方、血液の細胞と申しますもの、ことに赤血球と申しますものは、その中に核もございません。核があるなしは、細胞の生き死にということとかなり密接な関係がございます。したがいまして、赤血球の、最後にからだを回っておりますときの役目は、肺に行って酸素と炭酸ガスを交換するに必要なヘモグロビンというものを持ってからだを回って歩いておるわけでございます。オルソドックスな説必ずしも正しくはないかもしれませんけれども、われわれが食べましたものから血となり、肉となる、これはある意味で真理だと思います。しかし、血液というものは、そういう赤血球のほかに血奨というものがあって、それで栄養を方々へ送っておるわけでございます。その血奨は、確かに腸管から取り入れた養分を運んで適当なところへ持っていっております。そういう意味で、そういう死んだ細胞が、どういうことか知りませんが、お考えは自由でございますけれども、それがガンのもとをなし、また、それが血液に返っていくというような考え方というものは、われわれの医学常識ではちょっと考えられない。ですから、それは実験をしてくださるとおっしゃれば、そういう場面もあっていいかと思いますけれども、少なくともガンというものはどういうものか、そしてそれは、確かに、いまおっしゃったように、
大家である先生が見ても見つからない。これは幾らもあることで、われわれも大いに反省して、大いに努力をして、もっと勉強しなければいけないと思っておりますが、そういう研究としてまだまだわれわれが取り上げなければならないたくさんの問題がありますし、そういう意味も含めて根本の問題も考えていただくということはたいへんけっこうだと私は思います。ただ、いままでの学説が非常におかしくて、新しい説がぽんと出てくれば、それをなぜ取り上げないかという、
それだけの議論というものは、いろいろな立場から考えがあると思うのです。
問題は、そういう意味で、私たちも大いに勉強はしてまいりますけれども、もう一つ重大な問題は、骨髄ではなくて腸から血液ができる。それは少なくとも私たちが習い――これは何も、外国のまねをしているとか、そういう意味じゃございません。胎生期には、血液というものは方々でできてきます。子供のときはまだ長骨でもできます。しかし、おとなになりますと、血液というものは、ある一定の量があれば足りるものですから、それで、血液をつくっているのはおもに、
背骨にある短い骨の骨髄でありまして、そこを取って細胞を見ますと、血液の最小のものであるような非常に未熟な細胞から順序を追って最後の血液までの細胞
が発見されます。そういうことが、われわれが血液が骨髄でできているという説を支持しておることのおもな原因だというふうに御了解いただきたいと思いま
す。
○三宅委員
病院長から承りたいのですが、私のさっき話しましたことは全く私のしろうとの勘でありますから、違っておるかもしれませんけれども、先ほど申しましたとおり、小児ガンというものは最近非常に注目されている。最近非常にふえている。これは単に診療技術の進歩によってその発見が多くなされてきたというだけではない。私はそれほどガンの診断がおくれておるとは思いません。しかしそれだけではなくて、私の勘では、いま申しましたように、空気の中における近代産業の悪い公害的な影響だとか、農薬の中における影響だとか、いろいろのそういう影響があるのではないかという勘がいたしますが、実際上診断されたり研究されたりしたあなた方の判断におきましても、どうして急に最近子供のガンがふえてきて、そして、その原因は大体どこにあるかという点についてちょっと御答弁をいただきます。
○塚本説明員
これはさいぜん私同じことを申し上げたのでございますが、三宅委員がまだおいでになりませんでしたので……。
一説によりますと、非常に微量にふえておる放射線というような環境も関係がありはしないかという説もございます。これもはっきりしたことではございません。もちろんそういう意味で、全部いろいろなそういうものを含めた環境的な因子というものを否定できないということが一つ。
それから、先ほどちょっと申し上げました白血病というものは、わが国は、諸外国に比べますと、ふえたようでもまだぐっと低い状態でありまして、これも説でありますからあまりはっきりしませんけれども、たん白食を多くとると、つまり国民の栄養が上がってくると、むしろ白血病はふえるのだという説もございます。これの真偽も、私は自分で調べたわけでございませんのでわかりませんが、動物実験でそういう結果を、ネズミの白血病について出している学者がございます。
○三宅委員
ありがとうございました。
○三木(喜)委員
関連。関連ですから簡単に伺わしていただきたいのですが、いま三宅先生の質問の中にこういうことがあったのです。公害等によってその発ガンということを促進さしておる、こういうことはないかというお話ですね。これはお答えがなかったのですが、私は、幸いにその方面の研究をしておられる森下先生が見えておりますから、ひとつ聞かしていただきたいと思います。と申しますのは、この間動物園の動物が次々にガンで死んでおる。ああいう非常に野性味を持ったものがガンで死ぬということは、やはり現在のこの空気中に何かそういう発ガンを促進するようなものがあるのではないか、こういうぐあいのことを、これも三宅先生ではありませんけれども、しろうと的に考えるのです。なお、このごろのいろいろな調味料の中にガンを促進さすものがあるということ、森下先生の研究の中にもはっきり出ておるわけです。名前を一々あげるといけませんから、ある有名な飲料のごときは、そういう役割りをしておるといわれておるわけですね。これは私は、やはり厚生省からおいでいただいて十分そういうものを取り締まっていただかなかったら、うそつき商品が出たからといって、それであわてて取り締まる、こういうことではもうおそいと思うのです。そういう食料からくる問題、それから公害からくる問題、こういうことについてひとつ森下先生のお話を聞かしていただきたいと思います。
○森下参考人
いまおっしゃられましたように、大気汚染であるとか、あるいは排気ガス、ばい煙というようなものが肺ガンの原因になっている であろうということは、十分に想像されるところであると思います。私が調査した範囲では、去年上野動物園の動物が四十何匹か、これはいろいろの種類の動物でありますが、肺ガンだけではありませんが、ガン性の病気で死んでいるということであります。もちろん、こういう動物は別にたばこを吸っているわけではございませんが、実際に肺ガンで死んでいる。その原因は那辺にあるのかということでありますけれども、やはり一番大きな問題は、彼らが自然な環境から離れて人間がこしらえた不自然な食べものをあてがわれながら、しかも、こういう不自然な大気汚染の中で生活を強制されているというところにあると思います。したがいまして、動物の文明病といいますのは、これはガンだけではございません。たとえば、豚がコレラにかかるとか、あるいは牛が結核にかかるとか、あるいは動物園などではキリンが胃かいようで死んだりカバが糖尿病で死んだり、犬がノイローゼぎみであったりというように、人間社会の中でいろいろな病気を起こして死んでいっている、その動物たちの文明病の起源というものが人間の文明病の起源でもあるというふうに考えるべきだと思います。そういう広い立場に立って私たちは、特にガンだけをということではなくて、文明病対策というものはもっと大きな立場でわれわれ考える必要があるのではないかというようなことをいままで唱えてまいったわけであります。
たとえば、栄養問題もそうであります。現在唱えられておる栄養学に対しましては、私自身非常に大きな間違いがあるということを長年唱えてまいりました。そのほかにも、いろいろ問題があるわけでありますが、とにかく、もっと巨視的に、大きな観点というものを踏んまえて、そうして、こういう病気の対策というものを考えていかなければ、コップの中の小さな思索では問題は解決しないというような気がいたします。
それから、ついでにここで私、はっきり申し上げておきたいと思いますことは、ただいま塚本先生が血液の問題についていろいろ意見をお述べになっていらっしゃいました。これは全くそのとおりであります。現代医学のピークに立っておられる先生でありますから、既成概念の頂点に立っていらっしゃる方であります
から、既成概念を否定するということは、とりもなおさず、御自分の存在を否定するということにもつながるわけでありまして、それはとうてい私はできないことだと思います。しかし、たとえば、いま塚本先生がおっしゃられた考え方の中に、
赤血球が成熟その極限に到達した細胞である、これは現在の血液学の定説でありますが、この考え方が私はそもそも間違いである。
私の考え方では、食べものが材料になって腸でつくられた細胞でありますから、
きわめて原始的な細胞であります。
しかるがゆえに赤血球の中には何十種類もの酵素があり、しかも、エネルギーがプールされている。
最近これはわかった事柄であります。いままでは極端に成熟をした、老いぼれの、死の一歩手前の細胞であるという考え方で赤血球を見ていたわけでありますが、その考え方にそもそも大きな間違いがあると思います。最近の生化学の進歩は、赤血球の中の無数の酵素が含まれている、あるいは、エネルギーがちゃんとプールされていて、死ぬまぎわの細胞がなぜそういうものを持っているのか、いまの医学的な常識では説明がつかないという段階であります。そういうことから考えましても、もう根本的にやはり考え方の土台が違っているというような気がいたします。
それからガン細胞の分裂についてであります。いま塚本先生がおっしゃいましたように、ガン細胞というものは、体細胞が突然変異を起こして異常な細胞になって、その細胞が無限に分裂増殖をする細胞であるというふうに説明をされました。これは現在のガンに関する定義であります。世界の学者が、ガンとはそういう病気であるというふうに信じております。そういう意味ではもちろん間違いのない考え方でありますが、しかし私の立場から申し上げますと、そういうことももちろん承知の上で、
からだの中にあるガン組織というものは、私は分裂増殖をしておらない
というふうに見ております。しかし、実際にガン細胞の分裂がきれいに映画の中にとらえられたりしております。東京シネマでつくられましたガン細胞に関する映画などを見ますと、ガン細胞の分裂というものは実にみごとにとらえられております。が、それはそういう特殊なガン細胞が示す行動であって、すべてのガンがそういうふうに体内で分裂増殖をしているのではないと思います。もしガン細胞がほんとうに分裂増殖をしているのであれば、たとえば、現在がんセンターで入院あるいは手術をされたガンの患者さんのその組織の一片を持ってきて、そして顕微鏡の下でガン細胞の分裂というものは観察されてしかるべきであります。しかし、そういう観察がなされたという報告は、私は一例も聞いておりません。実際に手術をして、ガンの組織というものは幾らでも、いつでも、随意にわれわれは取り出すことができるわけでありますから、そういうガン細胞が分裂増殖をしているかどうかということは、確かめようと思えばいつでも確かめられるはずであります。そういう実際のガンの組織というものを取り出して、そして、顕微鏡の下でそれを観察した学者というものは、私はいないと思います。実際には、われわれのからだの中では、定説はガン細胞の分裂ということでありますけれども、赤血球がガン細胞に変わっていることは、ほぼ間違いのない事実だと私は確信いたします。実際に、最近フランスでも、ガン研究の権威であるアルぺルン教授が、ガン細胞というものが分裂しているかどうかということについては、これは詳しく触れておりませんけれども、小さなガンの種になる細胞が寄り集まって、そうして一個の典型的なガン細胞に発展をしていくのだという説を唱えまして、そういう報道がヨーロッパではなされております。そういうことを見ましても、分裂増殖だけではなさそうである。分裂増殖一辺倒ではいけないのではないか。たとえば、現在のガンの治療薬にいたしましても、ガン細胞は分裂増殖をするから、その分裂を抑制するような化学物質であればガンはなおるであろうというふうに、きわめて単純に、機械的に考えてその開発が進められ
ているわけでありますが、こういう考え方のもとでは、私は幾ら研究費をつぎ込んでもしかるべき抗ガン剤というものはできないというふうに見ております。また、いままで長年私はそういう考え方を講演会で述べたり、あるいは私の著書の中ではっきりと明記いたしております。
ガン細胞が赤血球からできるということにつきましては、私が八年前に書きました「血球の起原」という本の中でそれをはっきり述べております。たとえば、吉田肉腫の場合でありますが、あの吉田肉腫の細胞というものは、実際にはほとんど分裂増殖をしておりません。種を動物の腹腔の中に植えつけますと、まず必ず腹膜に出血性の炎症が起こってまいります。そして、腹腔の中にまず血液が浸出する、赤血球が腹水の中にたくさんまざり始めるということを前提にして、初めてガン細胞はふえるのであります。
吉田肉腫の細胞というものは増殖していっております。その過程を、私は八年前に書いた私の本の中ではっきり指摘いたしております。吉田肉腫の増殖というものも、私は、腹膜の炎症が起こらなければ、腹膜の炎症を起こさないように処置してこの吉田肉腫の種を植えつけたのでは、絶対にこの肉腫細胞は増殖をしないであろうというふうに想像いたしております。
炎症というものが背景にあって、血液が腹水の中に出てくるということが 前提条件である、そうしなければガン細胞はできない、その赤血球がお互いに融合し合いまして、そうして一つのガン細胞に発展をしていくということであります。
また、実際にこの吉田肉腫の細胞を観察してみますと、形がまちまちであります。もし一定の分裂方式で細胞が増殖していくのであれば、ほとんどきまった形の細胞ができなければならないのに、増殖している細胞は全く千差万別であるということも、でき方が単に分裂増殖ではないということを物語っているように思
われます。
それから、話はだいぶ前にさかのぼりますが、さっき斎藤議員が申しておられました無菌的な血液を培養して、そうして点状の小さなバクテリアが発生をし、
これが球菌になり、桿菌に発展をしていくことが実際にあるのかどうか、これは国の機関でひとつはっきりさせろということを申しておられましたが、この問題
につきましては、私自身すでに、SICの牛山氏とは全然別個に実験を行なっております。私はSICの問題とは一切無関係に、血液というものは無菌的な条件
のもとで、試験管の中で放置しておけば、一体最後にはどういうふうに変わってしまうものであろうかというようなことを追求する目的で、大学時代に大ぜいの
研究員を使いまして、こまかく探索をいたしました。その結果は、この八年前に書きました「血球の起原」という本の一〇〇ページ、それから今度出しました
「血液とガン」という本の一五ぺ-ジに、その写真も掲載をいたしまして、その結論を披瀝いたしておりますが、これは無菌的な血液であっても、血漿の中に、
これは実は赤血球の中にそういう点状のバクテリア様のものが発生をいたしまして、これがだんだん発育をいたしまして、そうして球菌になり、かつ、桿菌にま
で発展をするという事実を私は認めております。
この問題は、国家の機関で追求せよということでありますけれども、私はその必要はほとんどないのではないかというような、むしろ逆の考え方をしておりま
す。といいますのは、はっきりとそういうふうになるのでありまして、牛山氏が無菌的に血液を培養して、ああいう桿菌様のものが得られたというその事実に対
しましては、私は絶対に間違いがなかったというふうに判定できると思います。
ただ、そういう桿菌様のものを材料にしてつくられたSICという化学物質がガンにきくかどうかということは、私は臨床医でありませんので、これは全くわかりません。そういうことをこの際つけ加えておきたいと思います。
○齋藤(憲)委員
もうだいぶ時間が過ぎましたから、あとの農薬問題に割愛をいたしまして、他日またこの問題でひとつ実態を突き詰めてまいりたい、そう思っておりますが、塚本国立がんセンター病院長のお話は、私の考えておったとおりのことをお話し願ったわけです。私もそう思っておった。そう思っておって、あらゆるガンに対する施設というものに対しては、私も興味を持ってずいぶん努力をした一人であります。放射線医学総合研究所の設立なんかに対しましては、私なんかもずいぶん努力をいたしましてやったのでありますけれども、なかなか放射線だけでガンを退治するという理論も実際もまだ生まれてきていない。どんどんガン患者はふえていく。同僚島口代議士もつい先日ガンでなくなられて、あした追悼演説があるというようなわけであります。
ただこの際、私、委員長及び先輩同僚の委員の方にもお願いしておきたいのでありますが、これは森下学説とそれから塚本病院長のお話は根本的に違うのです。どうしてこういうものが同じ医学博士でおって違うのかというぐらいに違う。これは全くふしぎなんですね。私は何げなくこれを読んでおったのですけれども、話を聞くとそうなんです。
赤血球は極度に成熟分化を遂げた細胞、すなわちエンドセルであって、ヘモグロビン現象だけでもって酸素を運ぶだけにしか役立たないというのは、院長のおっしゃるとおりなんですね。
ところが、それが根本的な間違いだと書いてある。大体、医者で、医学博士という肩書きを持っておって、赤血球の実体もよくわからぬというのはおかしいじゃないですか。そうでしょう。一体なぜ赤血球の実体というものを把握しないのかと私は思うのですよ。
もし森下学説が正しくして、赤血球というものが幾多の機能を持っておって、これが一切の人間の組織を構成していくのだということが立証されたとしたら、いままでのお医者はどうするのですか。いままでの医学者というのはどうするのですか。腹を切らなくちゃならない。それから、血液だって、もう人間の血液というものは、
できてしまうとあまり要らないのだから、骨髄でもって血をつくっているんだという説一方は食うものがどんどん血になっていくんだと、
これも全く反対なんです。私なんか大食いのほうですから、食ったものは血となって、やはりその血のために細胞が新陳代謝しているんだと思っているのです。また、そうでなければこの肉体というものは保っていかないわけなんですね。だから去年の人はことしの人じゃない。一年間たつと全部細胞が新陳代謝してしまう、その新陳代謝の原動力は血だ、そうすれば年を取れば年を取るほど若い細胞をつくろうというには血が要るわけでしょう。成人は血が一ぱいになれば、あとたくさん要らないのだから、骨髄でちょこちょこやったらいいなんていう、そんな説は私は賛成しないのです。だから、お話を承れば承るほど、きょうの森下学説というものと既存の学説というものは対立して、これは別なものです。そういう中に、何を対象として一体ガン対策の金を二十七億円も出しておるかということなんです。
効果があがっていればいいですよ。一つも効果があがらないじゃないか。ますますガン患者はふえている。ガンというものはわからないのだからというて許されているけれども、ほかの科学技術振興に対する金の使い方でこんなことがあったら一体どうなる。この間三木先生から、ラムダ1、2、3は失敗したのでもって東京大学は痛棒を食ったのです。ガンはどうだ。毎年二十億、三十億の金を使っておって、だんだんガン患者がふえていく、そういうことに対してやはり行政庁としては、新しい根拠ある説というものは勇敢に取り上げて、これの実験を追求していくというところに、新しいガン対策というものが見出されるのでしょう。これはまあ行政庁にひとつお願いをしておきたいのです。
私の崇敬する加藤与五郎という理学博士がおられた。この方は昨年九十五歳でなくなった。三百も特許を取られた。が、しかし、その特許を取られた、その特許、発明をどうしてされたかというと、ずっと研究をしていって、研究をしていって目標がわからなくなったときに、その辺から枝道に入ったんじゃ研究というものは成り立たないのだという。出発点まで戻ってこい。そして、研究の目標というものが正しいか正しくないかということを再検討して、また新しい研究体制を形づくらなければ新しい分野というものは見出し得ないということを私は聞いたのです。
だから、ガン対策も、いままで一生懸命やったけれども効果はあがらないのだから、世界的にあがらないことは確かなんだから、そのあがらない原因を追求していると、白血球の問題、造血の問題そういう問題が出てきた。だから、ある意味においては、一方、一つの研究体制として出発まで下がってきて、腸の造血説と、それから赤血球、白血球の問題、そういう問題を真剣に、森下学説というものは正しいのか正しくないのかということを追求するということは、ガン対策として非常に大切なんじゃないか。私、これに書いてあったものですから「血球の起原」という本をゆうべさがして読んでみました。これだけの血液の研究をしている本が日本にほかにあったらひとつ病院長紹介してください。これはずいぶんりっぱな研究をしたと私は見ている。だから、こと血液に関してこれだけの研究をしておられる方が、赤血球というものは、ある場合においてガン細胞に変化していくのだ、だからガン細胞は分裂増殖しないのだ、そういうことが正しいか正しくないかということは私は追求できると思う。そこに新しい根拠が見出されればまたガンの新しい研究体制も樹立されると、こう思うのでありますが、どうかひとつ委員長におかれまして、この問題は、三宅先輩の言われるように、大切な問題だということをお取り上げくださいまして、また機会あるごとにこの問題に対して論議を重ね得られるようにお取り計らいを願いたいと思います。
どうもありがとうございました。